- 開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」
- 「Hello Kitty展 ―わたしが変わるとキティも変わる―」
- 「遊牧のくらしとテキスタイル―バローチを中心に―」
- 「モネ 睡蓮のとき」
- 「オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術」
- 「第73回 東京藝術大学 卒業・修了作品展」
- 「拓本のたのしみ」
- 「読み解こう!北斎も描いた江戸のカレンダー」
- 「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」
- 「ひとを描く」
- 「石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 マティスのアトリエ」
- 「異端の奇才――ビアズリー」
- 次「歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」
- 「魂を込めた円空仏―飛騨・千光寺を中心にして―」
- 「瑞祥のかたち」
- 「生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」
- 「ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965」
- 「没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ」
- 「企画展 花器のある風景」
- 「開館記念展 Ⅱ(破) 琳派から近代洋画へ―数寄者と芸術パトロン 即翁、酒井億尋」
- 「須田悦弘展」
- 「古筆切」
- 「特別展 片桐石州 -江戸の武家の茶-」
- 特別展「HAPPYな日本美術―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ―」
- 「仏教美学 柳宗悦が見届けたもの」
- 「生誕190年記念 豊原国周」
- 「茶道具取り合せ展」
- 「中国の陶芸展」
- 「『月映』とその時代 ―1910年代日本の創作版画」
- 「生誕135年 愛しのマン・レイ」
- 「アブソリュート・チェアーズ」
開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」
東京国立博物館、2025年1月21日から3月16日まで。
2026年に開創1150年を迎える大覚寺。その記念に先駆けて、東京国立博物館で大規模な特別展が開催されます。後水尾天皇ゆかりの宸殿を彩る狩野山楽による障壁画や、歴代天皇の書、明円作「五大明王像」など、平安時代から江戸時代にかけての貴重な美術品が一挙に公開される豪華な内容です。華やかな御所ゆかりの絵画や密教美術の名品に触れながら、大覚寺の長い歴史と信仰の世界を体感できるこの機会をお見逃しなく。
「Hello Kitty展 ―わたしが変わるとキティも変わる―」
東京国立博物館、2月24日まで。
ハローキティの50周年を記念する展覧会が話題沸騰中!キティちゃんの進化の裏には、ファンとの絆がありました。本展では歴代グッズの展示はもちろん、アーティストたちとのコラボ作品や映像コンテンツでその魅力を徹底解剖!会場内には、キュートなフォトスポットも満載です。あなたの思い出のキティちゃんや、新たな発見がきっと見つかるはず。大人も子どもも一緒に楽しめるこの展覧会、ぜひ足を運んでみてくださいね。
「遊牧のくらしとテキスタイル―バローチを中心に―」
東京国立博物館、2月16日まで。
遊牧民の暮らしと手仕事に迫る興味深い展示も開催中!バローチを中心とした遊牧民が生み出したテキスタイルは、移動生活に寄り添う工夫や美しさにあふれています。本展では、伝統的な織物や文様の技法をはじめ、生活に根ざした袋物や敷物が紹介されるほか、収集家・松島きよえ氏が撮影した貴重な写真も展示。遊牧民のリアルな日常や壮大な自然の風景を感じられる内容です。彼らの文化や暮らしの魅力にぜひ触れてみてください。
「モネ 睡蓮のとき」
国立西洋美術館、2月11日まで。
日本初公開を含むモネの〈睡蓮〉約50点が一堂に集まる、国内最大規模の展覧会。パリのマルモッタン・モネ美術館から貴重な作品が来日し、モネが追求した光と水、自然の美が堪能できる贅沢な展示です。繰り返し描かれた〈睡蓮〉には、モネの人生や芸術への情熱が凝縮されています。色彩が織りなす静謐で幻想的な世界に包まれながら、モネの視点で自然を感じてみませんか?美術ファン必見の展覧会です!
「オーガスタス・ジョンとその時代—松方コレクションから見た近代イギリス美術」
国立西洋美術館、2月11日まで。
イギリスの世紀転換期にスポットを当て、松方コレクションの名品を中心にオーガスタス・ジョンとその同時代の芸術家たちを紹介する展覧会。新たな美術運動が生まれる中、ジョンの卓越したデッサン力や大胆な色彩、ボヘミアン的感性が輝きます。素描や版画、油彩画を通じて、イギリス近代美術の多彩な動きを紐解く内容に注目です!美術界の変遷を追いながら、ジョンの魅力をぜひ体感してください。
「第73回 東京藝術大学 卒業・修了作品展」
東京藝術大学大学美術館、1月28日から2月1日まで。
日本の芸術界を担う若き才能たちの集大成が一堂に会する、東京藝術大学の卒業・修了作品展。今年で73回目を迎えるこの展覧会では、美術学部の全学科が参加し、絵画や彫刻、デザイン、映像など幅広いジャンルの作品が展示されます。東京都美術館や大学美術館、アトリエスペースなど多彩な会場を活用した力作の数々に圧倒されること間違いなし!未来を切り開く新星たちのエネルギーを感じてください。
「拓本のたのしみ」
台東区立書道博物館、1月4日から。
失われた名品の記録を紙に写し取った「拓本」の魅力に迫る展示が書道博物館で開催中。王羲之や顔真卿といった歴史的書家の名作や、原石が失われた貴重な作品など、国内外の貴重な拓本が集結します。拓本の歴史や制作技法を学びながら、その美しい文字や文様に酔いしれること間違いなし。書の文化を深く楽しめるこの展覧会、初心者から愛好家までおすすめです。
「読み解こう!北斎も描いた江戸のカレンダー」
すみだ北斎美術館、3月2日まで。
江戸時代に大流行した絵暦(えごよみ)の魅力に触れるユニークな展覧会。太陰太陽暦を基にした暦の仕組みや、ユーモア溢れる大小の月の隠し方が楽しい摺物が展示されています。浮世絵の巨匠・北斎も手掛けたこれらの作品には、江戸の人々の機知と文化が詰まっています。どこにヒントが隠されているのかを探しながら、江戸時代の生活とデザインの豊かさを存分に楽しんでください!
「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」
東京都現代美術館、3月30日まで。
日本初となる最大規模の坂本龍一展。音楽家・アーティストとして時代を切り開いた坂本が追求してきた「音と時間」のテーマを体感型インスタレーションで表現します。未発表の新作を含む10点以上の作品が館内外にダイナミックに展開され、音を「空間に設置する」という彼の挑戦を実感できる貴重な機会。五感で楽しむ新たなアート体験をぜひお楽しみください!
「ひとを描く」
アーティゾン美術館、2月9日まで。
人物を描くことの魅力を追求する展覧会。古代ギリシアの説話から近代ヨーロッパの絵画まで、85点を通じて人物表現の豊かさを紹介します。マネやセザンヌの自画像、ルノワールの肖像画など、画家の技法や個性が光る作品が勢ぞろい。また、ギリシア陶器に描かれた物語の人物像も見どころです。石橋財団コレクションの名品を通じて、時代を超えた「人を描く」ことの魅力に触れてみてください!
「石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 マティスのアトリエ」
アーティゾン美術館、2月9日まで。
石橋財団コレクションの名品《踊り子とロカイユの肘かけ椅子、黒の背景》にちなみ、アンリ・マティスのアトリエをテーマにした特集展示が開催中。アトリエはマティスにとって生活と創作が地続きとなる特別な空間でした。本展では、彼の創作活動を支えたインスピレーションの源や、室内を彩るデザインの工夫に迫ります。マティスのアトリエから生まれた色彩豊かな世界を、ぜひ体感してみてください!
「異端の奇才――ビアズリー」
三菱一号館美術館、2月15日から。
19世紀末の英国で異彩を放ったオーブリー・ビアズリーの芸術をたどる特別展。繊細な線描と白黒の大胆なコントラストで魅了する彼の作品は、欧米の美術界を騒然とさせました。日本の芸術家や漫画家にも、影響を受けた人が多いですよね。本展では、代表作『サロメ』や初期の挿絵、彩色ポスターなど約200点を展示。短命ながらも鮮烈な足跡を残したビアズリーの世界を、ぜひ会場でお楽しみください。
次「歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」
静嘉堂文庫美術館、1月25日から。
静嘉堂所蔵の名品でたどる役者絵の展覧会。役者絵は美人画と並ぶ、浮世絵の大きなジャンルでした。初期浮世絵から錦絵時代、明治錦絵までの流れを網羅し、歌舞伎と浮世絵の深い結びつきを解説します。注目は幕末明治期の浮世絵の傑作「錦絵帖」10冊余りの初公開。歌舞伎の華やかな世界と浮世絵の繊細な美しさに魅了される時間をお楽しみください。
「魂を込めた円空仏―飛騨・千光寺を中心にして―」
三井記念美術館、2月1日から。
江戸時代前期に独特の木彫仏を生み出した円空の世界を紹介する展覧会。木肌やノミ痕を活かした力強い造形は、現代彫刻にも通じる魅力があります。大注目は、呪術回戦にも登場した、「両面宿儺像」。岐阜県千光寺に所蔵される像なので、美術館の展示で見られる機会はめったにありません。貴重な作品とともに、円空の祈りや美意識を感じ取れるこの機会をお見逃しなく!
「瑞祥のかたち」
皇居三の丸尚蔵館、1月4日から。
古代中国や日本の文化に根ざした「瑞祥」の世界を探る展覧会。蓬莱山、鳳凰、麒麟など、めでたいことの訪れを象徴する霊獣や理想郷の造形美がずらりと並びます。絵画や工芸に込められた幸福や泰平の願いが、美しい形と色彩で表現された作品の数々に心を打たれます。吉祥の意味を学びつつ、古代から現代まで続く豊かな文化に触れてみてください。
「生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」
東京ステーションギャラリー、1月25日から。
日常の中にアートを見出した宮脇綾子の作品を紹介する展覧会。主婦として見慣れた野菜や魚をモチーフに、布や紙を用いた独自の手法で作品を創り上げた彼女。細部まで観察し、構造を分解して作り上げた作品は、美術とデザインの融合そのものです。親しみやすさの中に潜む高い完成度と命の輝きを感じられる宮脇綾子の作品世界を、ぜひお楽しみください。
「ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965」
パナソニック汐留美術館、1月11日から。
近代建築の巨匠ル・コルビュジエの芸術観に迫る特別展が開催中!後期作品を中心に、絵画、彫刻、タペストリーなど「諸芸術の綜合」と名付けられた多彩な試みを紹介します。建築を超えた調和と普遍性を追求したコルビュジエの革新的なアプローチに加え、レジェやカンディンスキーら同時代の作品と並べることで、彼の位置づけを紐解きます。「住む機械」を超えたコルビュジエの世界観をぜひ体感してください。
「没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ」
サントリー美術館、2月15日から。
ナンシーを拠点にガラス、陶器、家具で名を馳せたエミール・ガレ。こちらの展覧会では、彼を成功へ導いたパリとの関係に焦点を当て、ガレの芸術とそのジレンマを探ります。パリ万国博覧会での新作発表や富裕層とのつながりを物語る貴重なガラスや家具、初公開の資料など110点を展示。ガレの創造性と国際的成功の裏側を感じられる機会をお見逃しなく。
「企画展 花器のある風景」
泉屋博古館東京、1月25日から。
茶道や華道の中で進化した花器の美をたどる展覧会が開催中!室町時代の《砂張舟形釣花入》や江戸期の《古銅象耳花入》など、住友コレクションの名品に加え、華道家・大郷理明氏のコレクションも初公開。中国伝来の唐物から日本独自の美意識が花開いた花器の歴史を、実物と絵画の展示で楽しめます。日本の伝統美に触れるひとときをぜひお楽しみください。
「開館記念展 Ⅱ(破) 琳派から近代洋画へ―数寄者と芸術パトロン 即翁、酒井億尋」
荏原 畠山美術館、1月18日から。
琳派を代表する作品が一堂に会する展覧会が開幕!重要文化財「金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻」や「躑躅図」をはじめ、琳派の系統を網羅的に紹介します。さらに、洋画家を志した即翁の甥・酒井億尋のコレクションも展示され、近代の洋画から印象派の流れまで幅広い芸術を楽しめます。琳派と近代美術を結ぶ貴重な展示は必見です。
「須田悦弘展」
渋谷区立松濤美術館、2月2日まで。
木彫アーティスト須田悦弘の個展が松濤美術館で開催中!自然を感じさせる繊細な木彫作品と美術館の独特な建築空間がどのように調和するのか注目です。空間と一体化した須田の作品世界を体感しにぜひ足を運んでください。
「古筆切」
根津美術館、2月9日まで。
平安から鎌倉時代の和様書を中心に、名筆の美しさを紹介する展覧会。重要文化財「高野切」などの古筆切を展示し、それぞれの書が持つ独特の魅力を堪能できます。書の文化と歴史を感じるこの貴重な展示をぜひご覧ください。
「特別展 片桐石州 -江戸の武家の茶-」
根津美術館、2月22日から。
江戸前期の大名茶人・片桐石州を中心に、武家社会に広がった茶の世界を探る展覧会が開催!石州流茶道の美学や、数寄屋坊主としての彼の活躍を振り返る内容です。茶の湯における武家の文化を知る絶好の機会をお楽しみください。
特別展「HAPPYな日本美術―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ―」
山種美術館、2月24日まで。
長寿や繁栄など「幸福」をテーマにした展示が話題!伊藤若冲の《鶴図》や川端龍子の《百子図》など、見る人を幸せにする作品が勢ぞろい。2025年の干支にちなむ蛇の絵も見どころです。楽しくラッキーな日本美術を体感しにぜひ足を運んでみてください。
「仏教美学 柳宗悦が見届けたもの」
日本民芸館、1月12日から。
仏教美学を追求した柳宗悦の軌跡をたどる展覧会が開催。彼の主著『美の法門』に基づき、具体的な作物と資料を展示。初上映される講義映像も見どころです。柳が見た「美」の深淵に触れてみてください。
「生誕190年記念 豊原国周」
太田記念美術館、2月1日から。
浮世絵師・豊原国周の画業を振り返る展覧会が開幕。役者絵や美人画を中心に、国周の人気と才能が光る作品群を紹介します。明治の浮世絵の魅力をぜひ堪能してください。
「茶道具取り合せ展」
五島美術館、2月16日まで。
館蔵茶道具を中心に、茶室の床の間を再現した展示が話題。武野紹鷗や千利休ゆかりの名品や茶碗を中心に、茶事に用いる道具を展観します。茶の湯の美と技に触れるこの展覧会をお楽しみください。
「中国の陶芸展」
五島美術館、2月22日から。
漢から明・清時代にわたる中国陶磁器の名品を約60点展示。唐三彩、宋砧青磁、明代青花など、やきものの歴史を時代順にたどります。特集展示では刀剣コレクションも同時公開。中国陶芸の魅力を存分にご堪能ください。
「『月映』とその時代 ―1910年代日本の創作版画」
町田市立国際版画美術館、1月5日から。
1910年代の創作版画誌『月映』を特集する展覧会が開催中。恩地孝四郎ら若き版画家たちの情熱が込められた作品を展示し、同時代の版画表現と共に紹介します。大正期の生命観あふれるアートに触れてみてください。
「生誕135年 愛しのマン・レイ」
東京富士美術館、1月11日から。
多彩な才能を持つマン・レイの軌跡を追う展覧会が開催。画家、写真家、オブジェ作家など、多彩な顔をもったマルチアーティストとして活躍したマン・レイ。作品や資料を通して彼の人間性と芸術の魅力を紹介します。陽気でユニークな彼の世界をぜひ楽しんでください!
「アブソリュート・チェアーズ」
埼玉県立近代美術館、2月17日から。
「椅子」をテーマにした新感覚の展覧会。主に戦後から現代までの美術作品における椅子の表現に着目し、デザイン椅子だけでなく、アートの中で椅子が持つ象徴的な意味や役割を紹介します。日常の椅子が新たな視点で語りかける、刺激的な展示をお見逃しなく!


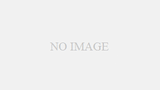
コメント